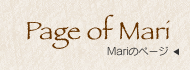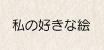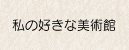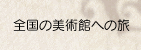「最後の晩餐」
イエスが「あなたがたのうちの一人が私を裏切ろうとしている」と告げた瞬間、弟子たちの間に戸惑いと動揺が広がります。ある者は困惑し、ある者は頭を抱え、それぞれに思いを巡らせています。唯一、長いテーブルのこちら側に座ったイスカリオテのユダだけは表情が読み取れません。彼は既に褒美の銀貨を受け取っています。孤独に仲間から目をそらすだけです。
マタイによる福音書第26章やヨハネによる福音書第13章に記された「最後の晩餐」の物語は、あまりにも多くの画家によって描かれてきた馴染みのあるテーマです。それぞれの画家が熟考し、取り組んできたに相違ないこの宴の舞台を、15世紀イタリアの画家アンドレア・デル・カスターニョ(1421年頃 – 1457年)は大理石や特徴的な彫像で飾りました。
殊に、壁に嵌め込まれた大理石のパネルは独特で印象的です。「なぜここにこれが?」と思わせるのですが、中世では不人気だった大理石はルネサンス期ににわかに注目されていました。古代のギリシャ・ローマを想起させることから、建材として富裕層の邸宅に用いられることも多くなっていたのです。そのあたりの時代性のキャッチもカスターニョは巧みだったのかもしれません。
アンドレア・デル・カスターニョはフィレンツェで生まれたとされています。そして彼の活動のほとんどはフィレンツェ周辺に集約されています。実は彼の生涯に関する詳細な情報は現在ではあまり多くないのですが、歴史的な記録からも彼が15世紀ルネサンスの重要な画家だったことは明らかです。
特筆すべきは、フィレンツェとミラノの戦争が始まるとコレリアに疎開し、戦争が終わった1440年、フィレンツェに移り、ベルナデット・デ・メディチの保護を受けたことは知られています。そこでカスターニョはアンギアーリの戦いで絞首刑に処された市民たちの肖像をポデスタ宮の正面に描き、それにより「Andrea degli Impiccati(首くくりのアンドレア)」というニックネームを頂戴しています。
彼は初期ルネサンスにおける技法やスタイルを守りながら、独自の芸術的視点を発展させた画家だったのです。特に感情表現や人物の立体感、さらに光と影のコントラストに非常にこだわっていました。ルネサンスにおけるリアリズムの発展を推し進めた画家だったことはもっと周知されるべきかもしれません。
この印象的な作品はフィレンツェのサンタポッローニア修道院の食堂に描かれたフレスコ画ですが、カスターニョの才能を最もよく表していると言われています。均整の取れた人物配置のなか、各人物の感情や表情に非常に細かな配慮をし、絵画を通して心理的なドラマを表現しています。
殊に特徴的なのは使徒たちの手の動きかもしれません。十二使徒たちは、向かいに座す形となる2人の手のポーズが鏡に映したように対比しています。そのリズミカルなリアリズムは魅力的です。服の色からポーズまでがバランスよく作品に貢献しているといえます。唯一、イスカリオテのユダだけが異質で孤独な存在として暗く重く描かれています。
ところで、十二使徒というのは、「イエスに使徒として召された」人たちと言われていますが、もちろん実際にはもっと多くの人々がイエスに付き従っていたと思われます。これを12人とはっきりと区切りをつけたのは福音書記者であったルカでした。集まった人々の中からイエス自身が12人を選んだと記述しており、さらに『旧約聖書』の時代ではイスラエルの部族がちょうど12存在したことも、「12」にこだわりを示した理由だったかと思われます。
この作品では、向かって左側から小ヤコブ、ピリポ、トマス、大ヤコブ、ペテロ、ユダ、ヨハネ、アンデレ、バルトロマイ、タダイ、シモン、マタイという並びとなります。
小ヤコブは「アルパヨの子ヤコブ」とされています。初代エルサレム司教となりました。「主の兄弟」とも呼ばれ、絵画の中ではしばしばイエスに容姿が似ることがあります。
ピリポはスキタイ地方の神殿で、ドラゴンを追い出す奇跡を起こしましたが、神官の怒りを買って磔刑になります。
トマスは使徒の中でただ1人、イエスの復活を信じませんでした。その後、トマスがイエスの脇腹の傷の傷に触れて納得する場面は、「トマスの不信」というテーマで多くの画家に描かれました。今ふうに言えば、めんどくさいヤツということになります。
大ヤコブは「ゼベダイの子ヤコブ」とも呼ばれます。聖ヨハネの兄で、もっともイエスに近かったとされる弟子でした。ヘロデ王によって処刑されましたが、9世紀に入って大ヤコブの遺体とされるものがスペインで発見されました。この奇跡の地は「サンティアゴ・デ・コンポステーラ」で、このため、スペインの守護聖人とされています。この地はカトリックの3大巡礼地の一つに数えられています。
ペテロは「第1の使徒」と呼ばれています。元漁師であり、弟のアンデレとともにガリラヤ湖で漁をしていてイエスに声をかけられ、弟子となりました。イエスが捕らえられたとき、思わず他人のふりをしてしまった逸話は「ペテロの否認」のテーマで多く描かれています。しかし、キリスト教団を設立し、初代のローマ教皇とみなされています。彼のアトリビュートは「天国の鍵」です。
ユダは「イスカリオテのユダ」と呼ばれています。彼の裏切りは「ユダの接吻」というテーマで、これもあまりにも多くの画家によって描かれています。イエスの顔を知らないユダヤ教の神殿警備隊の兵士たちに知らせるため、「ラビよ、安かれ」と言ってイエスに接吻するわけです。しかし、ユダはすぐに後悔します。報酬の銀貨も返そうとしますが祭司に拒絶され、結局みずから首を吊ることとなるのです。
ヨハネは「ゼベダイの子ヨハネ」、大ヤコブの弟です。もっとも若く、いつもイエスの傍で描かれます。「最後の晩餐」では、たいてい眠る姿で描かれます。福音書記者の1人です。
アンデレは、もとは洗礼者ヨハネの弟子だった人物です。ペテロの弟であり、兄をイエスに引き合わせたのもアンデレでした。殉教の折には、イエスと同じ刑具では申し訳ないと、X字型の十字架にかかることを望みました。
バルトロマイはイエスの昇天後、伝道の地アルメニアで皮剥ぎの刑によって殉教しています。そのため、アトリビュートは皮を剥ぐためのナイフです。皮を剥がれるなんて残酷でどんなに痛いだろうと想像すら出来ませんが、さすがキリスト教の聖人は無駄に死んだりしません。というのは、聖バルトロマイは皮剥ぎ職人、皮なめし職人、製本職人(中世の本は羊皮紙で作られていたため)など皮革関係の職人の守護聖人なのです。さらに、アルメニアでの殉教だったため、アルメニアの守護聖人でもあります。実際の名前はナタナエルというのではないかといわれています。
タダイの本名はユダ・タダイだったようです。タデウス、ファディとも表記されています。イエスを裏切ったイスカリオテのユダとの混同を避けるため、意図的に「タダイ」と呼ばれました。「ヤコブの子ユダ」とも呼ばれています。パレスチナ地方で伝道を続け、ペルシアで殉教しています。アトリビュートは処刑具の槍や棍棒です。
シモンは、タダイとともに福音を説いて伝道しました。熱心党というグループに属していたことから「熱心党のシモン」とも呼ばれています。 彼はカナン人であり、使徒のなかでも特に信仰が深く、モーセの律法を厳格に守っていたと言われています。殉教の処刑具はノコギリだったため、それが彼のアトリビュートとなっています。
そしてマタイは、『マタイ福音書』の書記者です。元徴税人であり、彼がイエスの弟子となる場面は、「マタイの召命」として知られています。また、シンボルとして表される場合、翼を持つ人間の姿で描かれています。
★★★★★★★
サンタポッローニア修道院 蔵
<このコメントを書くにあたって参考にさせていただいた書籍>
◎西洋美術史(美術出版ライブラリー 歴史編)
秋山聰(監修)、田中正之(監修) 美術出版社 (2021-12-21出版)
◎改訂版 西洋・日本美術史の基本
美術検定実行委員会 (編集) 美術出版社 (2014-5-19出版)
◎西洋美術館
小学館 (1999-12-10出版)
◎世界のビジネスエリートが身につける教養「西洋美術史」
木村 泰司 著 ダイヤモンド社 (2017-10-5出版)
◎聖書と神話の象徴図鑑
岡田温司 著 ナツメ社 (2011-10-15出版)
◎遠藤周作で読むイエスと十二人の弟子 (とんぼの本)
遠藤周作(編集) 新潮社 (2002-12-1出版)
カスターニョ,アンドレア・デル の作品
初期イタリア・ルネサンス の他の画家
- シニョレッリ,ルカ
- ロッビア,ルカ・デッラ
- フォッパ,ヴィンチェンツォ
- マルティーニ,フランチェスコ・ディ・ジョルジョ
- コッサ,フランチェスコ・デル
- ゴッツォリ,ベノッツォ・ディ・レーゼ
- ボッティチェリ,サンドロ
- ベッリーニ,ジェンティーレ
- ベッリーニ,ジョヴァンニ
- コネリアーノ,チーマ・ダ
- ブラマンテ,ドナート
- ギルランダイオ,ドメニコ
- ヴェネツィアーノ,ドメニコ
- ウッチェロ,パオロ
- ペルジーノ,ピエトロ
- ブルネレスキ,フィリッポ
- リッピ,フィリッポ
- クリヴェリ,カルロ
- トゥーラ,コズメ
- メッシーナ,アントネロ・ダ
- カスターニョ,アンドレア・デル
- ヴェロッキオ,アンドレア・デル
- マンテーニャ,アンドレア
- ポライウォーロ,アントニオ
- ベッリーニ,ヤーコポ
- ドナテッロ
- ピエロ・デラ・フランチェスカ
- フラ・アンジェリコ
- マザッチオ
- マゾリーノ